畳にカビが生えてショックを受け、どう掃除すればよいかわからず不安になる方は少なくありません。
間違った対処は見た目や臭いを悪化させるだけでなく、アレルギーや喘息の原因になったり畳素材を痛める可能性があります。
本文ではNHKの番組で示された科学的な考え方をベースに、家庭で安全にできる具体的な手順と注意点をやさしく解説します。
必要な道具、事前準備、軽度〜重度それぞれの掃除法、消毒と乾燥のコツ、素材別の対応と再発防止策まで順に紹介します。
写真や実践ポイントも交えて具体的に示すので、すぐに取りかかれます。
まずは原因の見極め方とすぐできる応急処置から読み進めてください。
ためしてガッテン流の畳のカビ対策と自宅での実践手順

ためしてガッテンで紹介される手法を日常の掃除に生かすコツをまとめます。
簡単で安全にできる段階別の対処法を、軽度から重度まで順を追って説明します。
必要な道具一覧
最初に道具をそろえておくと、作業がスムーズに進みます。
- ヘラ
- 柔らかいブラシ
- マイクロファイバー雑巾
- ゴム手袋
- マスク
- アルコールスプレー
- 重曹
- 扇風機または除湿機
道具は清潔なものを用意し、作業の前に消毒しておくと安心です。
事前の安全準備
カビ掃除では胞子を舞い上げない注意が最優先です。
換気扇を回すか窓を開け、室内の空気を入れ替えてください。
必ずマスクとゴム手袋を着用し、長袖の服で肌の露出を避けます。
畳周りに貴重品があれば移動し、作業スペースを確保してください。
小さなお子様やペットは作業中は別室へ移動してもらいましょう。
軽度カビの掃除手順
目に見えて薄く白っぽいカビが出ている場合は、軽度扱いで十分です。
乾いた柔らかいブラシで、カビの表面を優しく払い落とします。
払い落としたら、マイクロファイバー雑巾で畳の目に沿って拭き取ってください。
アルコールスプレーを布に吹き付け、拭き残しの部分を軽く消毒します。
最後に扇風機や窓開けで完全に乾燥させることが重要です。
中度カビの掃除手順
色が濃く広がっている場合は、中度としてより慎重に処置します。
まずブラシで浮いたカビを落とし、掃除機は使わないでください。
重曹を水で溶いたペーストをカビ部分に薄く塗り、5分ほど置きます。
その後、固く絞った雑巾で拭き取り、汚れを繰り返し取り除きます。
必要に応じてアルコールスプレーで仕上げ消毒を行い、その後十分に乾燥させます。
重度カビの応急処置
黒ずんだ広範囲のカビや、畳繊維に深く侵食している場合は重度です。
すぐに専門業者に相談することをおすすめしますが、応急処置は可能です。
まず周囲の人を避難させ、換気を最大にしてください。
カビの飛散を抑えるため、濡らした布で軽く覆ってから外へ運ぶ方法もあります。
畳自体の交換が必要なケースもあるため、写真を撮って業者に状況を伝えると判断が速くなります。
消毒と乾燥の方法
カビ除去後の消毒と乾燥は再発防止の要です。
以下の表は代表的な手法とポイントをまとめたものです。
| 方法 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| アルコール消毒 | 拭き取りが容易 | 変色注意 |
| 重曹水拭き | 臭い吸着効果 | 残留を拭き取り |
| 過酸化水素希釈 | 漂白効果あり | 素材テスト必須 |
| 熱風乾燥 | 短時間で乾燥 | 高温は避ける |
| 除湿機使用 | 安定した除湿が可能 | 長時間運転推奨 |
表にある方法を組み合わせると効果が高まります。
アルコールは表面消毒に適し、重曹は臭い対策に向いています。
乾燥は扇風機と除湿機を併用すると効率的に進みます。
除去後の消臭と点検
臭いが残る場合は重曹を撒いて数時間置き、掃除機で吸い取ると効果的です。
消臭剤を直接畳に吹きかける前に、素材に影響がないか目立たない場所で試してください。
24時間後に再度点検し、黒ずみや湿りが残っていないか確認します。
再発兆候があれば早めに専門業者に相談し、原因の根本対策を検討してください。
畳にカビが発生する主な原因

畳にカビが生えるのは単なる見た目の問題ではなく、住環境の健康にも影響する重要なサインです。
ここでは代表的な原因を分かりやすく解説し、日常で気をつけるポイントをお伝えします。
高湿度
畳表は天然素材であることが多く、湿度に敏感に反応します。
一般的に室内湿度が60パーセントを超えるとカビが繁殖しやすくなるとされています。
梅雨時や冬場の結露シーズンは特に要注意で、長時間そのままにすると短期間で広がることがあります。
換気不足
窓を閉め切ったままの時間が長いと、畳の表面と内部に湿気がこもりやすくなります。
特に夜間の就寝中は湿度が上がりやすく、換気をしないとカビのリスクが高まります。
定期的に空気の流れを作ることで、湿気を効率よく排出できます。
長時間の布団接触
畳と布団が長時間密着していると、布団側の湿気が畳に移ります。
日中に布団を上げない習慣があると、その部分だけ色や質感が変わり、カビが発生することが多いです。
布団を上げる時間や畳を直射日光に当てる時間を作るだけで、かなり予防効果があります。
畳下の結露
床下や畳の裏側で結露が発生すると、目に見えない部分からカビが広がることがあります。
特に断熱が不十分な床や冬季の暖房使用時に発生しやすい問題です。
| 発生要因 | 確認ポイント |
|---|---|
| 温度差 | 窓側の床 |
| 断熱不足 | 床下の湿り |
| 配管の水漏れ | 畳の裏側の異臭 |
畳の表面だけでなく、裏側や床下の状態まで点検することが再発防止につながります。
汚れ・皮脂の蓄積
汗や皮脂、食べこぼしが畳表に残ると、そこが栄養源となってカビが繁殖しやすくなります。
特に座ったまま過ごす場所や子どもが遊ぶ場所は注意が必要です。
- 汗の染み
- 皮脂の付着
- 食べこぼし
- 髪の毛やホコリ
定期的に軽く乾拭きする習慣をつけることで、汚れが原因のカビを防げます。
カビの種類別の見分け方と目安

畳に現れるカビには見た目や手触りである程度の種類が判別できます。
種類を早めに見分けることで、適切な対処と再発防止につながります。
白カビ
表面に白い粉状や綿状のものが広がっている場合は白カビの可能性が高いです。
軽く指先でこすると取れることが多く、初期段階であれば被害は浅いです。
発生は高湿度や換気不足が原因になっていることが多く、早めに乾燥させることが重要です。
- 白い粉状の斑点
- 触るとほろほろ取れる
- 広がりが速くない
- 悪臭がまだ弱い
家庭での対処は表面の乾拭きと十分な換気、除湿が基本です。
青緑カビ
青緑色や緑がかった斑点が点在する場合は青緑カビを疑ってください。
湿気を好む種類で、窓際や畳の端、布団が長時間触れる部分に発生しやすいです。
放置すると広がりやすく、色素が染み込んでシミになることがあります。
| 見た目 | 発見場所 | 対処の目安 |
|---|---|---|
| 青緑色の斑点 | 窓際や畳の縁 | 拭き取りと乾燥 |
| やや粘性がある | 布団接触部 | 中度以上は専門業者 |
初期なら乾燥とアルコールを薄めた拭き取りで改善することが多いです。
黒カビ
小さな黒い点が集合している、あるいは黒い斑点が拡大する場合は黒カビの疑いが強いです。
黒カビは色素が濃く、畳内部まで根を張ることがあるため厄介です。
健康被害も出やすく、特にアレルギー症状や呼吸器の不調を招く恐れがあります。
範囲が広い場合や床下まで侵食していると感じたら、専門のクリーニングや張替えを検討してください。
胞子繁殖による臭い
カビの増殖は目に見える変化より先に臭いで気づくことが多いです。
畳からの刺激臭やじめっとした匂いがする場合は胞子が増殖しているサインです。
臭いがある場所は胞子が飛散しやすく、掃除時に室内に拡散する危険があります。
まずは換気と除湿を行い、臭いが強い場合や体調不良が出る場合は専門業者に相談してください。
自宅でやってはいけないNG行為

畳のカビを見つけると、焦ってすぐに手を出したくなることが多いです。
しかし、誤った対処はカビを広げたり、畳自体を傷めたりする原因になります。
ここでは家庭でやりがちなNG行為を、理由と代替案を交えてわかりやすく説明します。
水拭き
濡れた布でゴシゴシ拭くと、表面に付着したカビを畳の繊維の奥へ押し込んでしまいます。
畳は吸湿性が高く、水分を含むと乾燥しにくくなるため、かえってカビを増やすことが多いです。
また、水分が残ると畳下の床板にまで湿気が伝わり、構造的なダメージを招く可能性があります。
表面のカビ汚れは、まず乾いた布ややわらかいブラシでそっとかき出すようにしてください。
掃除機での吸引
カビの胞子は微細で、掃除機で吸い込むと空気中に舞い上がる危険性があります。
胞子が室内に広がると、他の場所へ飛散して二次被害を招きやすくなります。
| 危険性 | 具体例 |
|---|---|
| 胞子の飛散 | 室内全体への拡散 |
| フィルター詰まり | 吸引力低下 |
| 畳表の損傷 | 表面繊維の摩耗 |
通常の掃除機はフィルターを通して微粒子を排気するため、逆効果になりやすいです。
どうしても掃除機を使う場合は、HEPAフィルター搭載の密閉型を使うか、専門業者に相談してください。
叩き落とす方法
畳を叩くと振動で胞子が空中に飛散し、隣接する部屋にも広がる恐れがあります。
強く叩く行為は畳表の織り目を緩め、繊維を痛めるため避けるべきです。
布団を叩くように力任せに行うのはNGで、代わりに粘着ローラーややわらかいブラシで表面の汚れを取り除いてください。
強酸や漂白剤の直塗布
酸や次亜塩素酸ナトリウムなどの強い薬品を濃いまま畳に塗ると、色落ちや繊維の分解が起こります。
さらに、揮発した薬剤が室内空間を汚染し、呼吸器や皮膚に悪影響を及ぼす可能性が高いです。
安全な代替手段として、次のような方法を検討してください。
- 70%アルコール希釈
- 重曹ペースト薄め
- 市販の畳用洗浄剤
- 専門業者による薬剤処理
薬剤を使う際は、必ず目立たない箇所で色落ちテストを行い、十分に換気しながら作業してください。
畳素材別の処置と注意点

畳の素材によってカビ対策の方法や使える洗剤が変わります。
ここでは代表的な三種類の畳表ごとに、家庭でできる対処法と注意点をわかりやすく解説します。
まずは目立たない箇所で必ず試験処理を行い、変色や傷みが出ないか確認してください。
イ草表畳
天然のイ草は風合いが良く、吸湿性も高い反面、水分や強い薬剤に弱い性質があります。
強く擦ると表面繊維が崩れて目立つ跡になるため、優しく扱うことが基本です。
次の道具を用意して作業してください。
- マイクロファイバー布
- 柔らかい豚毛ブラシ
- エタノール70パーセントのスプレー
- 中性洗剤を薄めた溶液
- 使い捨て手袋とマスク
- 扇風機または除湿機
乾いたブラシで表面のホコリや胞子を優しく払った後、エタノールを布に吹き付けて叩くように拭いてください。
エタノールで落ちない場合は、中性洗剤を薄めた布で軽く拭き、すぐに乾いた布で水分を取るようにしてください。
過度の水拭きや漂白剤は色落ちや変形の原因になりますので、使わないでください。
作業後は窓を開けて風を通し、扇風機や除湿機で完全に乾かすことをおすすめします。
和紙表畳
和紙表は技術的に強化されているものが多く、撥水加工や染色が施されている場合は比較的耐久性があります。
ただし表面のコーティングは傷つきやすいため、硬いブラシや強い溶剤は避けてください。
乾いた布で軽く拭き取り、取れない汚れやカビは布にエタノールを少量含ませて拭くと効果的です。
水を使う場合はごく少量にとどめ、拭いたらすぐに乾いた布で吸い取って乾燥させてください。
製品によっては水拭きが可能なタイプもあるので、メーカーの指示を確認するようにしてください。
樹脂表畳
樹脂表は水に強く、掃除や日常のケアがしやすいのが利点です。
中性洗剤を溶かしたぬるま湯で布拭きができ、汚れがひどい場合は少し強めに擦っても問題ない場合が多いです。
ただし長時間の濡れ放置は接着部に影響することがあるため、拭いた後は速やかに乾燥してください。
エタノールを用いて消毒しても色落ちや変形の心配が少ないですが、念のため目立たない箇所で試してください。
樹脂表は日頃の水拭きでカビ抑制がしやすく、手入れの頻度を上げることで再発を防ぎやすくなります。
畳表の張替え判断
表面のカビが激しく繰り返す場合や、素材自体が脆くなっていると感じるときは張替えを検討してください。
下記の表は、張替えの目安を簡潔にまとめたものです。
| 症状 | 張替えの目安 |
|---|---|
| 広範囲の黒カビ | 一度に除去できない場合は張替え検討 |
| 繊維の崩れや裂け | 耐久性低下のため張替え推奨 |
| 表面の著しい変色 | 美観回復のため張替えが有効 |
見た目以外に畳床まで湿気やカビが進行している場合は、裏返しや張替えで根本的な対策が必要になります。
迷うときは専門業者に点検を依頼し、費用対効果も含めて判断することをおすすめします。
再発を防ぐ日常管理
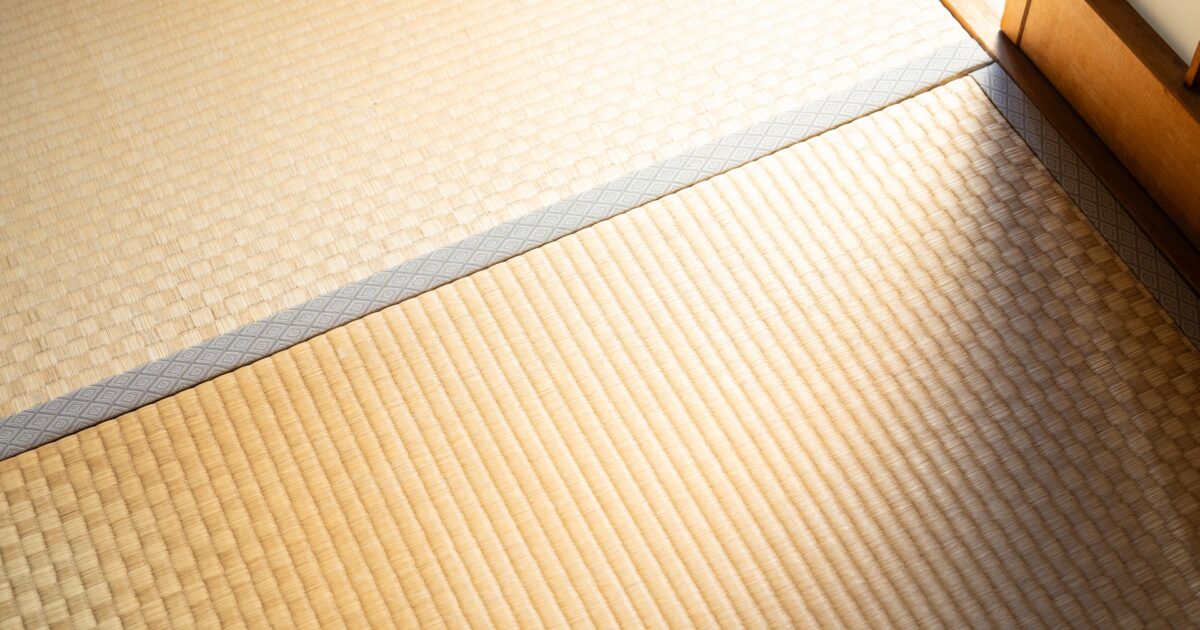
再発を防ぐには、日々のちょっとした習慣が最も効きます。
まず湿度管理を徹底してください、室内は概ね50〜60%以下を目安にし、除湿機やエアコンのドライ運転を活用します。
換気を毎日行い、特に入浴後や雨の日の後は窓を開けるか、機械換気で空気を入れ替えてください。
布団は畳と長時間密着させないで、日中は上げるか、こまめに干して湿気を抜きます。
畳表面は週に一度、柔らかいブラシや掃除機でほこりを払い、汚れが付いたら早めに拭き取り処理を行ってください。
畳の縁や周辺は見落としやすい場所ですから、月に一度は畳を上げて畳下の点検をすることをおすすめします。
防カビ剤や湿気取りシートを適所に置くと安心感が増しますが、使用方法は表示に従ってください。
早期発見が最も効果的ですから、変色やにおいを感じたら無理をせず、専門業者への相談も検討してください。

