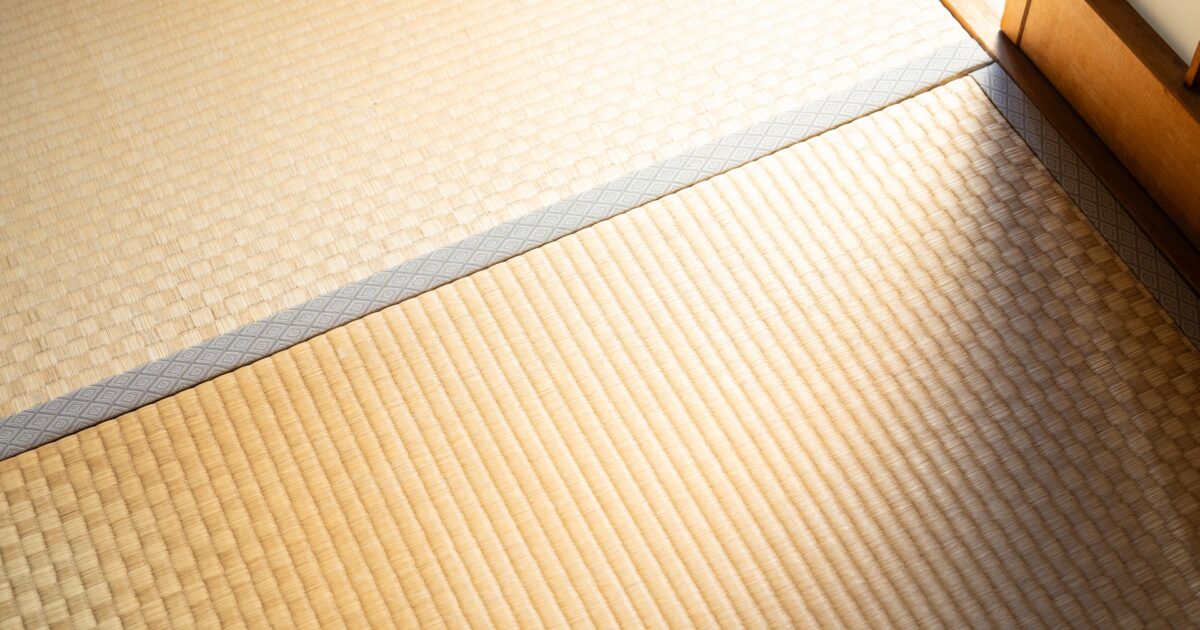畳のへこみや変形に悩んでいませんか。
重い家具や椅子の脚が長時間のせられると、見た目だけでなく暮らしの快適さも損なわれます。
そこで手軽に導入できるニトリのコルクマットを使った保護法を、メリットや推奨厚み、必要枚数の計算まで実例を交えて詳しくご紹介します。
設置場所の選び方やジョイント処理、通気対策、日々の掃除法といった実践的なポイントも網羅しています。
コルク以外の保護アイテムとの比較や、へこみや湿気が発生したときの対処法まで押さえられるので、続きで最適な敷き方を確認しましょう。
ニトリ製コルクマットで畳のへこみ防止を実践する

ニトリのコルクマットは畳を長持ちさせるための手軽な対策として注目を集めています。
見た目の馴染みやすさと衝撃吸収性が両立している点が大きな魅力です。
メリット
コルク素材は弾性があり、家具の重みを分散させることで畳への局所的なへこみを防ぎます。
ニトリ製品はカットのしやすさやジョイントの精度が高く、DIY感覚で敷ける利便性があります。
また天然素材に近い温かみのある見た目で和室の雰囲気を損ねにくいです。
推奨厚み
一般的には5mmから10mmの厚みが畳保護には適しています。
軽い家具や椅子のキャスターには5mm前後で十分な場合が多いです。
ソファや大型の家具のように荷重が集中する場合には8mm以上をおすすめします。
ただし厚みが増すと段差感が出るため、出入口や襖との兼ね合いを確認してください。
必要枚数計算
まず敷きたい範囲の縦横の長さを測っておきます。
ニトリのコルクマットの1枚あたりのサイズを確認し、縦横それぞれをマットの寸法で割ると必要枚数の概算が出ます。
| 部屋サイズの目安 | マット枚数の目安 |
|---|---|
| 6畳 | 24枚 |
| 4.5畳 | 18枚 |
| 3畳 | 12枚 |
切り欠きや出入口の形状により端材が出るため、計算上の枚数に1〜2割の余裕を持たせると安心です。
設置場所の選び方
へこみ防止の観点では、家具の脚が直接当たる箇所を優先して敷くと効果的です。
通路や出入り口は踏まれる回数が多いため、強度の高い厚みを選ぶか別素材で補強してください。
畳の傷みが気になる窓際や日当たりの強い場所は、湿気や変色も考慮して設置場所を決める必要があります。
ジョイント処理
マット同士の接合部は隙間ができるとそこから畳に負荷が集中する恐れがあります。
ニトリのジョイントははめ込み型で比較的ズレにくいですが、敷いた後に押し合わせて馴染ませることを忘れないでください。
長期間使用する場合は接合部に市販の連結用テープを併用するとズレ防止になります。
通気対策
コルクは天然素材で湿気を吸いやすいため、通気対策を怠ると畳の湿気トラブルにつながります。
敷きっぱなしにせず、週に一度は部分的にめくって下の畳を乾燥させてください。
また湿気が多い季節は除湿機や換気扇で室内の湿度を下げることが効果的です。
掃除とメンテナンス
日常的な掃除は掃除機やほうきで表面のホコリを取るだけで十分です。
- 掃除機で表面のゴミ除去
- 固く絞った雑巾で軽く拭く
- 汚れがひどい部分は中性洗剤を薄めて拭く
- 定期的にめくって畳の乾燥確認
水拭き後は乾拭きをして水分を残さないように注意してください。
長期間の使用で摩耗が出た場合は、部分的に交換することで畳への影響を最小限に抑えられます。
コルクマット以外の畳保護アイテム

畳を長持ちさせるために、コルクマット以外にも有効なアイテムが複数あります。
用途や予算に合わせて選べるので、組み合わせて使うのもおすすめです。
敷板
敷板は厚手の板材を畳の上に敷いて荷重を分散させる方法です。
耐荷重性が高く、重い家具のへこみを防ぎたい場合に向いています。
通気を確保しつつ使うことが大切で、直置きよりも多少の隙間を設けると湿気対策になります。
- 合板タイプ
- 桐製
- 樹脂製
- 滑り止め付き
- カット対応
設置は比較的簡単で、寸法に合わせてカットすればすぐに使えます。
保護シート
保護シートは薄手で扱いやすく、簡易的な保護に適しています。
防水性のあるタイプもあり、飲み物をこぼす可能性がある場所に便利です。
| 種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| ビニールシート 塩化ビニール |
耐水性あり 安価で扱いやすい |
| ラバーシート 合成ゴム |
クッション性あり 滑りにくい |
| 透明プロテクター PET系素材 |
目立ちにくい 傷防止に適する |
ただし、長期間畳と密着させると湿気やカビの原因になることがあるので注意が必要です。
フェルトパッド
フェルトパッドは椅子や家具の脚に貼るだけでへこみを軽減できます。
費用が安く、賃貸住まいでも導入しやすい点が魅力です。
接着タイプのものと差し込みタイプがあり、使用場所や取り替えのしやすさで選びます。
定期的に状態を確認し、毛羽立ちや汚れがひどくなったら交換してください。
家具滑り止め
家具滑り止めは移動の際に畳を傷つけにくくする目的で使います。
滑り止め自体が摩耗して畳を傷める場合もあるので、素材と厚みに注意が必要です。
ゴム製やシリコン製、粘着タイプと非粘着タイプがあるため、使用する家具に合わせて選んでください。
重い家具には滑り止めと敷板を併用すると、へこみとズレ防止の両面で効果的です。
ニトリ製品と他社製品の比較ポイント

ニトリのコルクマットは価格と使い勝手のバランスが良く、手軽に導入しやすい点が魅力です。
この記事では価格、耐久性、厚み、防湿性、接合方式の観点で、選び方のコツをわかりやすく解説します。
価格
ニトリは量販店ならではの低価格帯の商品が多く、初期コストを抑えたい方に向いています。
一方で、他社には高密度や表面処理にこだわったプレミアムラインがあり、長持ちや見た目を重視する場合は割高でも検討の価値があります。
重要なのは単価だけでなく、1平方メートルあたりのコストや付属品の有無で判断することです。
セール時期やまとめ買いで価格差が縮まることもありますから、購入タイミングを工夫すると良いでしょう。
耐久性
コルクマットの耐久性はコルクの密度や表面加工の有無で大きく変わります。
ニトリ製品は日常使用に耐える設計が多いものの、重い家具を長期間載せる用途ではへたりや摩耗が目立つ場合があります。
対して、他社の中には耐摩耗層を厚く取った商品や、表面にポリウレタン塗装を施した製品があり、耐久性が高い傾向です。
耐久性を重視するなら、実際の使用シーンを想定してサンプルや保証内容を確認すると安心です。
厚み
厚みはクッション性と荷重分散に直結しますが、厚いほど畳との間で湿気がこもりやすくなる点も留意が必要です。
| 厚みカテゴリ | ニトリの傾向 | 他社の傾向 |
|---|---|---|
| 薄手 | 3-5mm | 3-6mm |
| 中厚 | 6-8mm | 6-10mm |
| 厚手 | 9-12mm | 10-15mm |
目安として、ソファやチェアなど点で荷重がかかる場所には中厚以上を選ぶとへこみ軽減効果が高まります。
ただし厚みが増すと価格と取り回しの手間も増えますから、用途に合わせてバランスを取ることが大切です。
防湿性
コルク自体は天然素材で湿気に強い性質を持ちますが、裏面の素材や接着方法で通気性が変わります。
ニトリの製品は通気性を考慮した仕様のものが増えていますが、合成素材の裏打ちがあるタイプは畳と接したままにすると蒸れやすくなります。
他社の高級品では透湿性の高い構造や防カビ加工が施されることがあり、湿気が気になる環境では検討の余地があります。
対策としては敷設前に畳表の乾燥状態を確認し、定期的にマットを持ち上げて換気することをおすすめします。
接合方式
接合方式は設置のしやすさや仕上がりの見た目に直結します。
ニトリはパズル式のジョイントが主流で、DIY感覚で敷ける点が評価されています。
他社にはテープ固定やはめ込み式など多様な方式があり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
- パズルジョイント式
- はめ込み式
- 両面テープ固定式
- 滑り止め一体型
接合方式が違えば隙間の出方や継ぎ目の強度が変わりますので、部屋の形状や日常の使用頻度を踏まえて選択してください。
コルクマットの具体的な敷き方と設置手順

コルクマットを畳に敷くときの具体的な手順を、実践的なポイントとともにご案内します。
準備段階から仕上げまで順を追って説明しますので、初めての方でも安心して作業できる内容です。
設置前準備
まずは設置場所の寸法を正確に測ることが重要です。
畳の状態を確認して、湿気や汚れがないかをチェックしてください。
- 測定用メジャー
- コルクマット本体
- カッターナイフ
- 定規や角材
- 養生テープ
- 雑巾や掃除用品
購入したマットは開封して室内で数時間置き、素材をならしておくと敷きやすくなります。
畳面は掃除機や雑巾で埃を取り、完全に乾かしてから作業を始めてください。
並べ方の基本
一般的には部屋の一番奥の角から敷き始めると作業がスムーズです。
マットの柄や目地がある場合は、向きを揃えて見栄えを整えてください。
長手方向に一直線に並べる方法のほか、レンガ状にずらす敷き方も有効で、継ぎ目の強度を高められます。
ジョイント部分はしっかりと押し合わせ、隙間がないかを指先で確認しましょう。
隙間ができたときはゴムハンマーを当て布で保護し、軽く叩いて密着させると仕上がりが良くなります。
継ぎ目処理
継ぎ目は見た目と耐久性に直結するため、適切な処理を行うことが大切です。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| そのままジョイント カットで合わせる |
見た目が自然 手軽にできる |
| テープ補強 布テープ使用 |
ズレ防止効果大 処置が簡単 |
| 専用コネクター 固定力重視 |
耐久性が高い 取り外し容易 |
継ぎ目にテープを使う場合は、畳側へ接着剤が入らないように注意してください。
強い接着剤や粘着テープを直接畳に貼ると、跡や変色の原因になりますので避けると安心です。
端部のカット
窓枠や出入り口の段差に合わせて端部を丁寧にカットします。
まずは鉛筆でカットラインを引き、定規を当ててカッターで切ると仕上がりがきれいになります。
カットは少しずつ浅く切り進める方法が安全で、失敗を防ぎやすいです。
端の処理は段差が気になる場所に合わせてRを付けるか直線で仕上げ、仕上げ面はサンドペーパーで整えてください。
ドア下など可動部分がある場所は、マットが干渉しないよう少し余裕を持たせると良いです。
荷重分散の配置
重い家具を置く場所は、マットが長時間へこまないように配置を工夫してください。
家具の脚は可能な限り複数のマットにまたがるように配置すると、局所的な負担が軽減されます。
さらに安定性を高めたいときは、家具の下に薄い敷板や専用プレートを敷いて荷重を広く受ける方法がおすすめです。
頻繁に移動する椅子やキャスターのある家具には、キャスター用の受け皿や保護シートを併用すると畳へのダメージを抑えられます。
設置後は数週間ごとに配置を見直し、へこみやズレがないかを確認する習慣をつけると安心です。
へこみや湿気が発生したときの対処法

畳やコルクマットにへこみや湿気が生じたら、早めに点検して対処することが大切です。
放置すると状態が悪化して、補修費用が高くなることがありますので、段階的に対応しましょう。
小さなへこみ復元
まずは被害箇所の確認から始めてください。
家具の重みでできた浅いへこみは、家具を移動してから軽くマッサージするように押し戻すだけで改善する場合が多いです。
コルクマットの場合は、ドライヤーの温風を低温で当てながら、へこんだ部分を手や丸い棒で外側から内側へ軽く押すと弾力が回復することがあります。
畳のへこみは藁が詰まった芯材が圧縮されていることが多いため、蒸気で軽く湿らせて藁を膨らませる方法が有効な場合がありますが、水のかけすぎは避けてください。
処置後は風通しの良い場所で十分に乾燥させ、重いものを長時間同じ場所に置かないように注意しましょう。
大きなへこみ補修
へこみが深い場合や範囲が広い場合は自力での復元が難しいことが多いです。
まずはコルクマットやカバーをはがして、畳や下地の状態を詳しく確認してください。
畳の芯材が大きく潰れているときは、部分的な張り替えや表替えが必要になることがあり、専門業者に相談するのが安全です。
コルクマットが変形している場合は、交換用パネルと取り替えるか、下地に薄いクッション材を追加して荷重を分散する対策を検討してください。
補修費用や作業時間の目安を事前に確認して、必要なら複数社から見積もりを取ると安心です。
湿気除去
湿気の対策は早めに行うとカビや変色を予防できます。
- 窓を開けて換気をする
- 除湿機やエアコンの除湿運転を使う
- マットをめくって下を乾燥させる
- 湿気取り剤を設置する
- 直射日光を避けて陰干しする
特に梅雨時や冬場の結露が出やすい季節は、定期的にマットを上げて裏面を乾かす習慣をつけてください。
効果を高めるには、風の通り道を作るように家具の配置を見直すと良いです。
カビ除去
カビが見つかったら速やかに除去し、再発を防ぐ対策を行いましょう。
| 方法 | 注意点 |
|---|---|
| エタノール拭き | 目立たない場所で試す |
| 重曹ペースト | 優しくこする |
| 塩素系漂白剤希釈 | 色落ちに注意 |
| 専用カビ取り剤 | 説明書に従う |
| 専門業者の清掃 | 広範囲や深い侵食に対応 |
作業前には必ず目立たない箇所で変色や材質への影響を確認してください。
手袋やマスクを着用して作業し、換気を十分に行うことが重要です。
塩素系漂白剤は畳や一部のコルク素材で色落ちや変質を招くため、使用は最小限にとどめてください。
広範囲のカビや黒カビが深く根を張っている場合は、健康被害を避けるために専門業者へ依頼することをおすすめします。
購入前の最終チェックリスト

購入前に確認しておくべきポイントを、短く分かりやすくまとめました。
畳に合った保護効果や厚み、設置枚数、通気性の確保方法を押さえておくと、トラブルを防げます。
- 保護性能(厚みと材質)
- 必要枚数の計算(設置面積)
- 設置場所と家具の重さ
- 通気性の確保方法
- ジョイントの仕上がりと段差
- メンテナンスと交換目安
- 防湿・防カビ対策
上の項目をチェックリストとしてメモし、店頭や通販の仕様と照らし合わせてから購入してください。